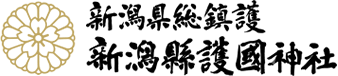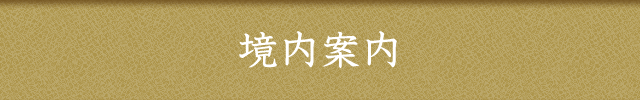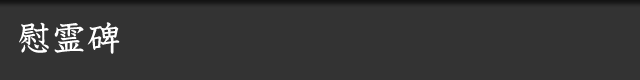当神社境内(参道両脇)には、戦友会をはじめとし各団体の方々が造られた慰霊碑がございます。
-

慰霊植樹の碑
歩兵第十六連隊第三機関銃中隊の昭和十五年兵戦友会によって建立された。当時、兵役は国民の義務であり、陸軍の兵役期間は現役2年間であった。昭和15年に入営した場合、最短でも昭和16年まで兵役に就いたはずである。歩兵第十六連隊は、昭和15年10月、中国から新発田市に帰還、昭和16年10月に臨時編成下令。それ以降は、大東亜戦争緒戦の昭和17年3月、蘭印ジャワ島の攻略作戦に参加、10月にはソロモン諸島ガダルカナル島に上陸して戦った。
-

植樹記念の碑
第十三師団歩兵第十六連隊第二歩兵砲小隊戦友会によって建立された。歩兵第十六連隊は、第二師団隷下の連隊であったが、明治41年から大正14年5月までは第十三師団に編入されていた。この間、大正8年9月に第十三師団隷下として動員され、シベリア出兵に参加した。大正10年5月には新発田市に帰還し、大正14年5月、再び第二師団に編入された。
-

軍馬の霊を慰む
(新潟県軍馬慰霊碑保存会)
古来より陸上戦闘の主役であった騎兵は20世紀初頭、機関銃や戦車の登場によってその価値を減じだ。しかし、各国陸軍の砲兵や輜重兵にとって、馬は依然として重要な輸送手段であった。日本陸軍でも馬を重要な輸送手段として位置づけ、日本各地の軍馬補充部で馬の飼育と調教を行い、軍馬として各地の戦場に送り出した。戦地での軍馬は実によく働き、世話をする日本軍将校と強い絆で結ばれていた。しかし、悪化する戦況で戦場での過酷な任務によって、殆どの軍馬は生きて再び戻ることはなかった。
-

鎮魂
(第13師団歩兵第116連隊第7中隊戦友会)
平成元年5月、第十三師団歩兵第百十連隊第七中隊戦友会によって建立された。歩兵第百十連隊は昭和12年9月第十三師団隷下として、新発田市の歩兵第十六連隊を基幹に編成された。同年10月に上海に上陸し、翌昭和13年以降、南京攻略、徐州会戦、武漢攻略に参加した。その後も中国各地を転戦して多くの作戦に参加し、昭和20年、中国の衝山で終戦を迎えた。
-

戦没軍犬慰霊碑
(軍犬慰霊碑保存会・元関東軍軍犬育成所所員一同)
平成2年4月、元関東軍軍犬養成所員によって建立された。軍犬の横顔が彫られている。軍用犬が組織的に使用されるようになったのは、20世紀初頭、第一次世界大戦後であった。日本陸軍でも大正8年から本格的に軍犬の養成を開始、その任務は伝令・警戒・捜索であった。軍犬は優れた運動能力や知覚能力、そして高い忠誠心によってこれらの任務を実によくこなし、部隊の将兵から非常に信頼された。しかし苛烈な戦場で多くの軍犬が命を落としていった。
-

近衛歩兵第二連隊軍旗拝受百周年記念碑
昭和49年8月、近歩二会新潟県支部によって建立された。近衛歩兵第二連隊は明治7年1月23日、近衛歩兵第三大隊と同第四大隊を基幹として編成され、軍旗を拝受した。近衛歩兵第一連隊と並んで日本陸軍最初の歩兵連隊であった。その後、西南戦争、日清戦争、日露戦争、支那事変に従軍した。大東亜戦争に於いては、緒戦のマレー半島の攻略に参加、その後は昭和20年に解隊するまで皇居北の丸に駐屯し、皇居の警備に任じた。
-

陸軍少年飛行兵新潟県出身戦没者慰霊碑
昭和60年11月に建立された。陸軍少年飛行兵制度とは昭和9年に始まった陸軍の航空要因を養成する制度であった。海軍の予科練と並んで当時の全国の少年たちの憧れであり、全国から優秀な人材が集まった。その為、非常に高い競争倍率であったという。終戦までの間に約45,000名の卒業生が巣立ち、陸軍航空の主力を担う下士官航空要員として各地の戦場で活躍した。題字は元内閣総理大臣中曽根康弘によるもの。
-

野戦重砲兵第15連隊之碑
野戦重砲兵第十五連隊は、昭和12年6月1日、朝鮮半島北部の羅南に於いて、第十九師団山砲兵第二十五隊第四大隊を基幹に編成され、留守第十九師団隷下の歩兵連隊となった。昭和20年2月、留守第十九師団と留守第二十師団の一部から第七十九師団が編成された。その際、野戦重砲兵第十五連隊は、同年4月8日に戦闘序列が下令された第十七方面軍隷下の第五十八軍第十二砲兵司令部の指揮下に移った。新編の第十七方面軍は、米軍の侵攻に備えて朝鮮半島の守備に就き、第五十八軍は東シナ海の済州島に配置され、そこで8月15日の終戦を迎えた。
-

予科練鎮魂の碑
(予科練鎮魂の碑保存会)
新潟県出身の海軍飛行予科練習生戦没者の慰霊の為に建立された。海軍飛行予科練習生制度は、昭和4年12月に制定され、翌年6月に第一期生が入隊、以後、3年間の教育で海軍航空隊下士官搭乗員の養成を行った。当時の少年たちにとって、予科練は陸軍少年飛行兵と並んで憧れの的であり、7つボタンの制服はそのシンボルであった。大東亜戦争末期、下士官搭乗員の不足を補うために募集人員が大幅に増やされたが訓練期間は短縮された。そして、多くの若者が特攻隊員として散っていった。
-

鎮魂慰霊之碑
(新潟県海交会)
平成7年、新潟県海交会によって建立された。海交会は旧日本海軍関係の方々による戦友会である。<碑>は、新潟県出身で戦没した海軍の軍人や軍属を慰霊する為に建てられた。大東亜戦争に於いて、海軍の軍人・軍属約47万名が祖国を護る為、島嶼や南海、そして空に散っていった。
-

空碧雲流の碑
(白鴎遺族会新潟県支部・海軍飛行予備学生 生徒有志)
平成9年9月新潟県出身の海軍飛行予備士官戦没者を慰霊するため、元海軍飛行予備学生の関係者によって建立された。海軍飛行予備学生制度は、旧制大学・高等専門学校を卒業した志願者から採用した予備士官制度で、昭和9年に第一期生5名が採用された。その後大東亜戦争での熾烈な航空戦による士官搭乗員を補う為に採用人数も増え、特に、昭和18年以降学徒出陣によって多数の学生が飛行科予備士官として馳せ参じた。戦死した海軍特攻隊員の8割以上は予備学生出身者であった。
-

平和慰霊
(近衛歩兵第1連隊有志)
平成6年3月、皇太子徳仁殿下と雅子妃殿下の御成婚記念と戦没者慰霊の為、新潟県出身の元近衛歩兵第一連隊関係者によって建立された。近衛歩兵第一連隊は陸軍最初の歩兵連隊として編成され、明治7年1月23日に軍旗を拝受。その後、西南戦争・日清戦争・支那事変に従軍した。大東亜戦争に於いては、緒戦のマレー半島攻略に参加、その後は昭和20年に解隊するまで、皇居北の丸に駐在し、警備に任じた。
-

植樹記念碑(慰霊之為)
(元歩兵第116連隊第2中隊有志)
歩兵第百十六連隊は、昭和12年9月第十三師団隷下として、新発田市の歩兵第十六連隊を基幹に編成された。同年10月に上海に上陸し、翌昭和13年以降、南京攻略、徐州会戦、武漢攻略に参加した。その後も中国各地を転戦して多くの作戦に参加し、昭和20年中国で終戦を迎えた。<碑>は平成3年4月15日に建立された。
-

第3中隊慰霊碑
(元歩兵第116連隊第3中隊有志)
歩兵第百十六連隊は、昭和12年9月第十三師団隷下として、新発田市の歩兵第十六連隊を基幹に編成された。同年10月に上海に上陸し、翌昭和13年以降、南京攻略、徐州会戦、武漢攻略に参加した。その後も中国各地を転戦して多くの作戦に参加し、昭和20年中国で終戦を迎えた。<碑>は平成5年8月15日に建立された。
-

慰霊塔
(近衛歩兵第三連隊有志)
近衛歩兵第三連隊は、明治18年に編成された近衛師団隷下の連隊であった。近衛師団は、天皇陛下と皇室の警護を目的として創設され、全国から選抜された優秀な将兵が配属された。近衛師団は、日清戦争・日露戦争・支那事変に従軍し、大東亜戦争緒戦に行われたマレー半島やシンガポール攻略作戦に参加した。横の<石碑>には、近衛歩兵第三連隊に於ける新潟県戦没者氏名が彫られている。
-

ソ連抑留本県出身者1600余柱の慰霊碑
(財団法人全国強制抑留者協会
新潟県支部慰霊碑設立委員会)平成5年5月、全国強制抑留者協会新潟県支部によって建立された。昭和20年8月9日、アメリカ・イギリスとの密約に基づき、ソ連軍は日ソ不可侵条約を一方的に破棄し、満州や千島列島に侵攻を開始した。そして、昭和20年8月15日に日本政府がポツダム宣言を受諾した後も、これを無視して戦闘を継続、更に、停戦後に武装解除した軍人軍属や民間人約107万名をシベリアに連行、数年間にわたって抑留し強制労働に従事させた。このシベリア抑留によって約34万名の日本軍将兵・軍属・民間人が死亡、新潟県でも約1,600名が還らなかった。
-

戊辰の役殉難者墓苑
明治元年に勃発した戊辰戦争に於いて、信越や東北の諸藩は旧幕府軍(東軍)として新政府軍(西軍)と戦った。西軍は明治元年7月25日に新潟県の松ケ崎に上陸、これに対する東軍(米沢藩・会津藩・庄内藩)との戦闘は29日まで続き、新潟市は焦土と化した。明治8年、新潟市常磐ヶ丘にこの時の西軍戦没者を祀る<招魂社>が建立され、昭和20年にこの<墓苑>に移された。また<墓苑>には、大東亜戦争における戦没者を慰霊するための<慰霊碑>も建てられている。
-

コヒマ戦没者の碑・ビルマ戦没者の碑
昭和19年3月~6月、印緬(インド・ビルマ)国境のインパールとコヒマで実施されたインパール作戦は、約30,000名の戦没者を出して敗走した。その多くは補給の途絶による餓死や病死であった。インパール作戦の結果、ビルマ方面の防衛線は崩壊、終戦までに同方面での戦没者は約180,000名に登る。<コヒマ戦没者の碑>は、昭和53年9月17日、独立輜重兵第五十五中隊の関係者によって建立された。<ビルマ戦没者碑>は昭和48年12月、ビルマ方面軍司令部員であった本間由雄氏によって建立された。
-

満州開拓殉難者の碑
明治38年9月の日露戦争の勝利によって、日本は満州(中国東北部)に於ける権益を国際的に認められた。以降、満州には多くの開拓団や開拓民が移住し、新天地の開墾に情熱を燃やした。併しながら、昭和20年8月9日、日ソ不可侵条約を無視してソ連軍が満州への侵攻を開始した。ソ連軍は非戦闘員であった開拓移民にも攻撃を加え、多くの開拓移民が死亡した。新潟県出身者だけでもその数は約5,000名に上った。<碑>は、昭和34年8月15日、新潟県開拓民自興会によって建立された。
-

綏芬河の碑
満州の開拓には、全国で満州開拓民青少年義勇隊が結成され、大勢の若者が参加した。新潟県からも、昭和18年6月、新潟県郷土中隊として299名が満州(中国東北部)に渡り、綏芬河義勇隊訓練所に入所した。しかし、昭和20年8月9日、ソ連軍が突如満州に侵攻を開始、綏芬河義勇隊訓練所でも無抵抗の隊員約40名がソ連軍に殺害され、その後も内地への逃避行に於いて多くの隊員が死亡した。<碑>は平成3年3月、元義勇隊有志によって建てられた。
-

平和の礎
(護国神社に対面して設置されてある)
大東亜戦争において、祖国の平和と郷土の繁栄を願って散華された新潟県の軍人、軍属、在外邦人、内地の戦災者の御霊を祀る為、昭和43年3月に建てられた。格子の扉を境に、外陣と内陣に分かれている。内陣には、散華された人々を表す<護国の柱>という<塔>があり、<塔>の前には平和を表す大理石の<礎石>がある。<礎石>の右側には祈りを表す<女性像>が左側には誓いを表す<男性像>がある。